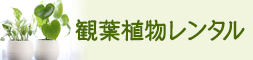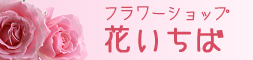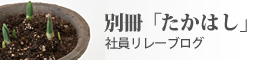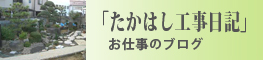ハーブ講座

|
10月に入ってもまだ30度近い気温です。さすがに、朝晩は涼しく秋を感じます。日が暮れるのも早くなりました。朝のひんやりとした空気の中、どこからかキンモクセイの香りが漂ってくるのに気が付きました。やはり季節を感じさせるかおりはいいものです。 今回はムラサキツメクサをご紹介します。 |
 |
| ムラサキツメクサ 英名 red clover 学名 Trifolium pratense 和名 ムラサキツメクサ 別名 アカツメクサ 、レッド・クローバー マメ科 多年草 ヨーロッパ原産で、日本にはシロツメクサ(Trifolium repens)と共に牧草として明治以降に渡来した帰化植物です。ヨーロッパの野原では良く見かけます。世界中に移入されていて、個体変異が大きく多くの変種があるようです。 日当たりよく、水はけも良い肥沃な土が適地です。個体差が大きく、全体の高さは20~80㎝位です。株元から褐色の茎が数本束生して、枝分かれします。葉は三出掌状複葉で互生し、小葉は楕円形で長さ2㎝位です。特徴的なのは、葉の表面に白いV字型の斑紋が見られることです。斑紋の形は不規則になり、葉や茎全体に毛があります。また葉には1~4㎝の葉柄があり、その基部には2枚の托葉が合着しています。頭状花序の下に1対の複葉がつくのも特徴です。 |
 |
|
5月から夏に花を咲かせます。茎の上方の葉腋に径約3㎝の頭状花をつけ、花が寄せ集まった集合花序となります。蕾は5裂した萼片に囲われていて、その1つはやけに長く、他の2倍位の長さです。しかも萼裂片全体に長毛が生えていて、あたかもフサフサした髪の毛の中から、ピンクの蕾が見え隠れしているような感じです。全部の花が出揃うと、萼片は花の中に埋もれてしまい、可愛いピンクの手毬のような形になります。花はマメ科特有の蝶型で、背後の旗弁は脈が透けて見え、また基部に行くほど徐々に色が薄くなるなど変化があります。じっくり見ると、とても美しいです。自然の美しさですね。そして、受粉して花が褐色になり果実になると、また長い萼裂片が目立ってきます。果実は萼筒の中なので直接は見えません。 |
 |
|
牧草や家畜飼料として栽培されます。また土壌を肥沃にする、空中窒素固定作用を持つマメ科の植物として、緑肥として使われます。(レンゲと同じ効用)そして、ムラサキツメクサには含まれる成分に薬効があり、薬用としても使用されています。 |
 |
次回はハマボウフウです。 |
グリーンアドバイザー
アロマテラピーインストラクター